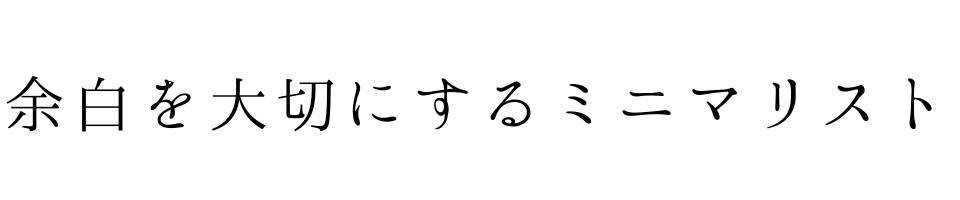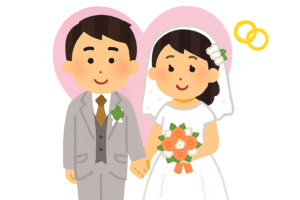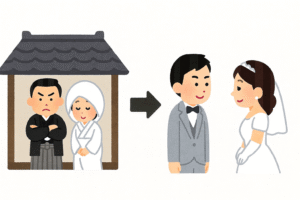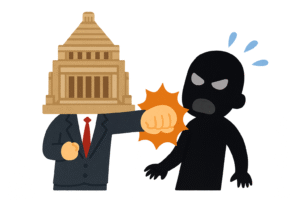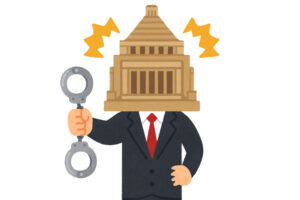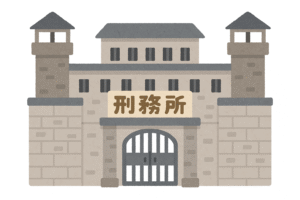生活共同体を営む夫婦への法的承認と保護?
現代の婚姻制度が、
子供を産み育てることを必須条件にしていない以上、
婚姻制度の目的について、
子供を産み育てる夫婦への法的承認と保護
と言い切ることは、適当ではありません。
生活共同体を営む夫婦への法的承認と保護
ということも、婚姻制度の目的だと言えるでしょう。
婚姻によって付与される義務と権利を分類

「婚姻」とは、二人が夫婦として共同生活を営むことについて合意をし、国家がその関係を認め、権利と義務を付与すること。
引用元:ChatGPT
婚姻制度によって付与される義務と権利について、
- 子供を産み育てる夫婦への法的承認と保護
- 生活共同体を営む夫婦への法的承認と保護
この二つの目的別に、分類してみようと思います。
 カネコ
カネコお時間のない方は、読み飛ばしていただいて構いません。笑
1. 子供を産み育てる夫婦への法的承認と保護
引用元:ChatGPT
- 嫡出推定:妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定される(父子関係の迅速確定)。これにより戸籍・相続・親権等の子の地位が安定します。
→ 民法772条(e-Gov)
※ 嫡出否認の規定(773~775条)も同じ条文群に含まれます。- 共同親権(婚姻中):未成年の子は父母の共同親権に服する(監護・教育・財産管理等)。
→ 民法818条(e-Gov)- 養子縁組の共同申立:夫婦が子を養子にする場合は原則として夫婦が共同で縁組する。
→ 民法795条(e-Gov)- 遺族基礎年金(子のある配偶者向け):被保険者死亡時、「子のある配偶者」又は「子」に給付。
→ 日本年金機構:遺族基礎年金
2. 生活共同体を営む夫婦への法的承認と保護
夫婦間の基本義務・債務関係
- 同居・協力・扶助義務 → 民法752条(e-Gov)
- 婚姻費用の分担 → 民法760条(e-Gov)
- 日常家事債務の連帯責任 → 民法761条(e-Gov)
- 貞操義務違反=離婚原因(不貞は裁判上の離婚事由) → 民法770条(e-Gov)
氏名・戸籍・親族関係
- 夫婦の氏 → 民法750条(e-Gov)
- 復氏(死別時に旧姓へ戻る) → 民法751条(e-Gov)
- 姻族関係終了 → 民法728条2項(e-Gov)
財産・住まい・相続
- 夫婦財産制(別産制) → 民法762条(e-Gov)
- 夫婦間の契約取消権(2024年改正で将来廃止予定) → 民法754条(e-Gov)
- 配偶者の相続権 → 民法890条(e-Gov)
- 配偶者居住権 → 民法1028条(e-Gov)
- 短期居住権 → 民法1037条(e-Gov)
- 借家の承継(内縁配偶者等) → 借地借家法36条(e-Gov)
税・社会保障
- 所得税の配偶者控除・特別控除 → 国税庁
- 相続税の配偶者の税額軽減 → 国税庁
- 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与) → 国税庁
- 健康保険の被扶養者認定(配偶者) → 協会けんぽ
- 国民年金の第3号被保険者 → 日本年金機構
- 遺族厚生年金 → 日本年金機構
裁判・刑事上の保護
- 配偶者の証言拒絶権(刑訴法147条) → 刑事訴訟法(e-Gov)
- 証言拒絶権(民訴法196条) → 民事訴訟法(e-Gov)
- 親族相盗例(刑法244条) → 刑法(e-Gov)
出入国管理(国際結婚)
引用元:ChatGPT
- 在留資格「日本人の配偶者等」 → 法務省
3. 両方の性格を有するもの
- 配偶者控除・特別控除(税制) → 国税庁
- 扶養控除 → 国税庁
- 児童手当 → 内閣府
- 出産育児一時金 → 協会けんぽ
- 遺族基礎年金 → 日本年金機構
- 遺族厚生年金 → 日本年金機構
- 扶養義務(夫婦・親子間) → 民法877条(e-Gov)
- 医療行為に関する同意(厚労省ガイドライン) → 厚労省
- 法定相続分(配偶者+子) → 民法900条(e-Gov)
※補足
子育て給付の多くは「婚姻不要」
児童手当・出産育児一時金・育児休業給付など、多くの子育て支援は「婚姻しているか否か」を要件にしていません(要件は“親子関係・被保険者資格・所得”など)。ここは「婚姻=子の保護だけが目的」という単線的理解とは異なるポイントです。
引用元:ChatGPT



結婚に興味がないので、今回初めて、こうして体系的に勉強することになりました。笑
こうして見ると、
現代の婚姻制度によって付与される義務と権利は、
生活共同体を営む夫婦への法的承認と保護
に分類されるものの割合が多いと言えます。
しかし、歴史を紐解けば、
婚姻制度の本質的な意義は、
時代に伴って変化してきたと思うのです。
続きます。