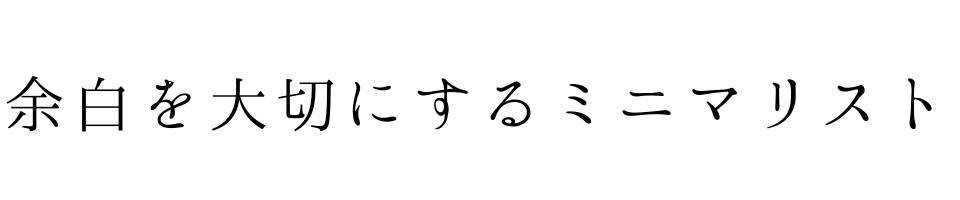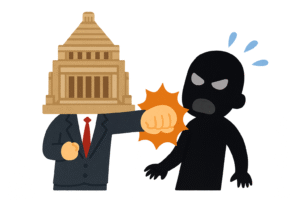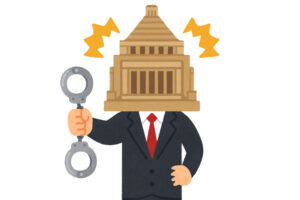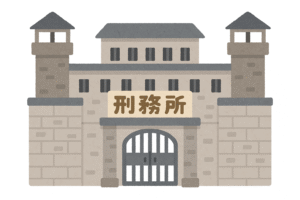同性婚のニュースを見た、結婚願望がない僕
こういうニュースを見て、
結婚・子育て願望が全くなく、
家族なんて煩わしい派の僕は、こう思いました。
 カネコ
カネコ『婚姻』って、男女が子供を産み育てることを前提とした法制度なんじゃないの?



ってか、なぜみんな、そんなに『結婚』したがるんだろう?
そこで今回は、
婚姻制度の『本質』について、
自分なりに考えてみようと思います。
子供を産み育てる夫婦への法的承認と保護?
婚姻制度の本質について考える上で、
最初にパッと思い浮かんだのは、これでした。



国力維持の為には、人口再生産が必要。



子供を産み育ててくれる夫婦に法的承認と保護を与えよう。
しかし、そうであるならば、
こうでなければ、論理的整合性が取れません。
しかし、
現在の婚姻制度では、
子供を持たない夫婦や、
子供を持てない夫婦にも、婚姻を認めています。
そう考えると、婚姻の本質や目的について、
子供を産み育てる夫婦への法的承認と保護
以外の視点についても検討する必要があります。
続きます。