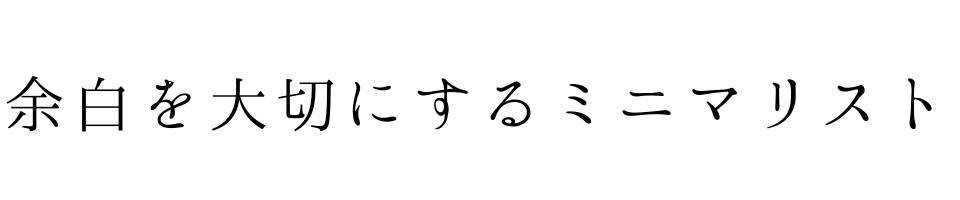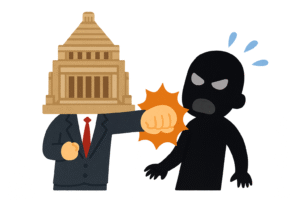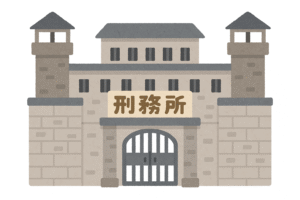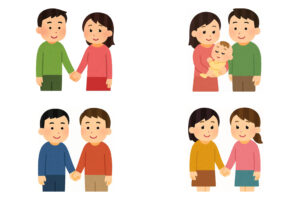刑罰の本質は『抑止』?
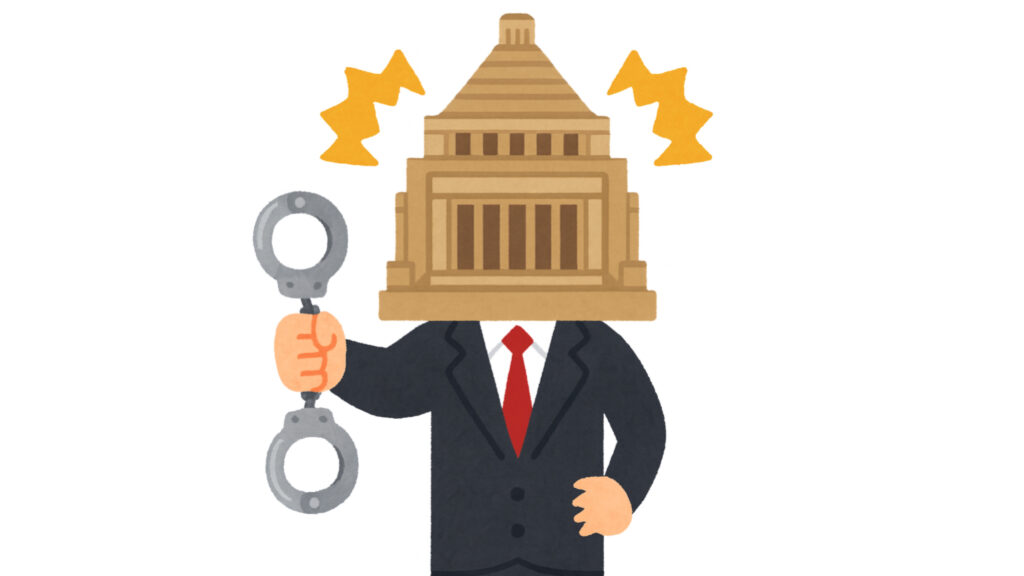
罰金、拘禁刑、死刑。
どの刑罰にも、一定の抑止効果は認められます。
 カネコ
カネコうーん…
『抑止』は、有力候補だな…
ですが、刑罰の本質を『抑止』だとすると、
少し、腑に落ちないところがあるのです。
シンガポール🇸🇬の刑罰への違和感
実は、抑止効果を重視して刑罰を設けているのが、
厳罰国家として有名な、シンガポール🇸🇬です。



以下に、
日本🇯🇵とシンガポール🇸🇬の
刑罰制度の違いについて、
分かりやすくまとめてみました。
① 死刑の適用範囲
- 日本:永山基準に基づき、極めて重大な殺人事件にのみ、慎重に判断される。死刑率は、全体の殺人事件の中ではごく一部。
- シンガポール:殺人は原則死刑。また、一定量以上の麻薬の所持・密輸でも死刑。
② 身体刑(鞭打ち刑)の存在
- 日本:憲法36条「残虐な刑罰の禁止」により、身体刑は存在しない。
- シンガポール:重犯罪だけでなく、性犯罪・強盗・暴行・器物損壊・不法移民などでも、実刑とあわせて鞭打ち刑が科される。
③ 麻薬犯罪への極めて厳しい態度
- 日本:覚せい剤取締法違反は懲役刑(通常数年)+罰金で済むことが多い。
- シンガポール:「麻薬は国家と社会を破壊するもの」と位置づけられており死刑が適用される。
④ 刑事裁判の傾向
- 日本:量刑判断では『応報』と『更生』の要素が重視される。
- シンガポール:量刑判断では『抑止』が最優先。
シンガポール🇸🇬の刑罰に、
僕が興味を持ったきっかけは、



シンガポール🇸🇬では、殺人は原則死刑になるらしい。



目には、目を。
歯には、歯を。
命には、命を。



シンガポール🇸🇬の刑罰は、素晴らしいなぁ✨
と思ったことでした。
ここで、一つ注釈を…
「目には目を、歯には歯を」は、実は、一般に誤解されている場合が多い言葉なんです。
古代バビロニアのハンムラビ法典に記されているこの言葉は、同害報復法とも呼ばれています。
一般的には「犯罪と同じやり方で報復せよ」というイメージで広まっていますが、実際の趣旨は「やりすぎの報復を制限せよ」 です。
つまり、「目を潰されたのなら、同じように目を潰すだけに留めておけ(命まで奪ってはいけない)よ」ということ。
無制限の復讐を防ぎ、刑罰・報復に比例原則を持ち込む のが本来の意味であり、「甘い罰を否定し、厳罰を推奨する」ではなく、逆に「過剰な罰を禁止する」という制約規範なんですね。
しかし、
シンガポール🇸🇬の刑罰について調べるうちに、



えっ!?
麻薬でも死刑?
器物損壊でも鞭打ち刑?



確かに、厳罰化すれば、抑止力は高まるとは思うけど…



罪に対する罰が重すぎるのは、おかしい。



目には、目を。
歯には、歯を。
この同害報復の原則を、超越してしまっている。
と思ったのです。
“同害報復”以上の厳罰で抑止力は高まる?
一般論としてですが、
厳罰化は、犯罪の抑止効果を高めると思います。



「飲酒運転の罰則を強化したら、検挙数が減った」というようなニュースを聞いたことがあるので…
もし、“同害報復”以上の厳罰化、
言わば『目には、命を』レベルの厳罰化で、
凶悪犯罪への抑止効果が高まるのなら、
刑罰の本質は『抑止』である
と言えるのかも知れません。
しかし、先日、素敵なフォロワーさんから、
非常に興味深い視点を、紹介していただきました。



実は、この方とは、以前Twitter上で、死刑について意見交換をしたことがありまして…笑
今回のブログ記事を、事前に読んでいただいたんです。笑
その方は、



基本的に、(冤罪のない前提で)殺人は原則死刑でいいと思っているんですが…
と前置きしつつ、
なぜ、“殺人に死刑一択”ではいけないのか?
について調べたことを、紹介してくださいました。
- 犯人が死刑を避けるためにどんな手を使ってでも逃げ、そのためにさらに犯罪を重ねて被害者が増える可能性。
- ヤケになった犯人が「どうせ死刑になるなら」とさらに犯罪を重ねる可能性。
- カッとなって被害者に怪我をさせた犯人が、身体刑の苦痛を恐れて「いっそ死刑の方が」とトドメをさしてしまう可能性
- 被害者に致命傷を負わせた直後に「なんてことをしてしまったんだ」と我を取り戻しても、死刑になることを恐れて被害者を救護せず逃げ、すぐに救護すれば助かったかも知れない命が助からなくなる可能性。
- 「無期懲役や身体刑は嫌だけれど死刑は別に構わない、むしろ殺してほしい」という人間が「確実に死刑にしてもらえるなら人を殺そう」と殺人に走る可能性。
この意見を聞いて、衝撃を受けました。



抑止効果を高めるために厳罰化しても、逆に新たな犯罪を誘発する可能性がある…だと?
刑罰の『抑止』機能の限界
刑罰には、犯罪の抑止効果が確かにあります。
厳罰化すれば、効果は一定程度高まるでしょう。
しかし、
刑罰の抑止効果は、完全ではありませんし、
抑止効果を重視して、極限まで厳罰化しても、
逆に、新たな犯罪を誘発する可能性すらある。
なぜなのか?
ここで一度、視点を変えて考えてみましょう。
そもそもの話、
我々は、なぜ犯罪をしないのでしょうか?
- 誰かに迷惑を掛ける、いけないことだから
- やってしまって、罰を受けるのが嫌だから
これを読んでくださっている人の多くは、
前者、つまりモラルの観点から、
犯罪をしない選択を、自然にしていると思います。
しかし、残念なことですが、
信じられない程、モラルの低い人間は存在します。
そのような人間に、犯罪を思い留まらせるために、
刑罰の抑止効果が、必要になってくるわけです。
しかし、さらに残念なことですが、
そのようなモラルが低い人間の中には、
罰を受ける “苦痛” よりも、
罪を犯す “快楽” を選択してしまうような、
常軌を逸した人間が、一定数存在するのも事実。
そのような人間に、
抑止効果は機能する確率は、限りなく低い。
ゆえに、
刑罰の抑止効果には、限界があるのです。
刑罰の本質は『抑止』ではない
『抑止』の機能
- “同害報復” 以上の厳罰への違和感
- 厳罰化しても抑止効果には限界がある
このような理由から、
『抑止』は、治安を維持する上で、
非常に重要な刑罰の機能ではあるけれど、
刑罰の本質ではないと、僕は考えました。
刑罰の本質は『応報』である
さて、
残る刑罰の機能は『応報』です。
この、最も “原始的” な刑罰の機能が、
刑罰の本質であると、僕は結論づけました。
続きます。